田村真依子(舞台照明技術者 2013年度人間科学科卒業生 大学祭実行委員会広報局長)
田口大(株式会社コヤマドライビングスクール 2013年度環境学科卒業生 大学祭実行委員会総務局長)
○2023年度実行委員
星野烈(日本文学文化学科4年 大学祭実行委員会広報局長)
松島大智(アントレプレナーシップ学科4年 大学祭実行委員会実行委員長)

「大変なこともあったけど、
みんなでつくろうという熱量がありました」
ーー本日は第13回黎明祭が開催されている有明キャンパスに、卒業生の田村真依子さん、田口大さんに来ていただきました。お二人は第1回黎明祭の実行委員をされていたとのこと。今回は、後輩の星野烈さん、松島大智さんと、思い出などを語り合っていただきたいと思います。まず、皆さんが担当していた役割を教えてください。
田口 (卒業生)
私は3年生のときに総務局の局長をやらせてもらいました。どのイベントをどこの建物で行うのか決めたり、各局や出店団体の要望を聞いたり、必要な備品や設備を準備したり、電気の配線管理もしたりと、大学祭全体の調整を担う局です。また僕は局長だったので、さまざまな仕事を局の皆に割り振りながら動いていました。ちょうど有明で最初の黎明祭をやる年度で、2つのキャンパスを午前・午後と行き来していました。けっこう大変でしたけど、何とかやり切ったことを覚えています。大学祭が終わってからも、じゃあ来年はどうしようかと、1年中大学祭のことを考えていましたね。
田村 (卒業生)
総務局は常に走り回っているイメージだよね(笑)。私が担当していた広報局の役割は主に、大学祭の宣伝や集客です。摩耶祭は学外のお店にポスターを貼ってくださいとお願いしたり、自転車で学校周辺の家にポスティングしたりしていましたが、黎明祭は摩耶祭の時とは環境が全く違って、広報に悩んだ覚えがあります。大学祭が始まる前にあちこちへの広報活動を終わらせて、当日は総務局の手となり足となり、手伝います!みたいな感じの局です。
星野(在学生)
僕も田村さんと同じ広報局長です。僕らの代で良かったことは委員の人数が多かった点ですね。実行委員自体は250人くらいいて、広報局だけで50人ほどいました。
田村(卒業生)
今はそんなにいるんですね。私たちの時はそんなにいなかったな。実行委員全体でも100人はいなかったな。
星野(在学生)
人数が多いことで新しくできたことも多かったんですけど、その分、まとめたり仕事を割り振ったりするのが大変でした。ただ、本番が近づくにつれて一致団結していこうみたいな雰囲気が自然と出てきたんです。みんなで一つのものをつくろうという熱量がありました。
松島(在学生)
ちょうど100周年の節目やコロナ明けということもあって委員が増えたことは嬉しかったけれど、想定以上だったので運営も大変だったよね。僕の委員長局も30人のメンバーで、書類のチェックや教職員の方々との打ち合わせを担当しました。大学祭当日は、一日中キャンパス内を回って問題がないかを確認して、各局から次々にかかってくる電話に対応して走り回っていました。僕は委員長としてオープニング挨拶も担当しました。
田口(卒業生)
当日、委員長は忙しいですよね。何かあるたびに電話来て。両方の耳で電話出て、訳分からなくなるみたいな(笑)。
松島(在学生)
そうなんですよね(笑)。オープニング挨拶前にも電話がかかってきて、てんやわんやでしたが、楽しかったです。

「ゼロからの黎明祭は、とにかく
たくさんの人を呼び込もうと必死でした」
星野(在学生)
黎明祭を初めて開催するというのは、どういった始まり方だったのですか?
田口(卒業生)
武蔵野キャンパス単独開催だった第44回摩耶祭が終わった後に、次をどうするか、話し合い始めました。だいぶ揉めました。
田村(卒業生)
だいぶ揉めたね(笑)。
田口(卒業生)
有明キャンパスでも大学祭を開きたいかどうかを学生にアンケートを取ったら、「開きたい」という声が多かったんです。それならやろうと動き出したものの、まず摩耶祭と黎明祭の実行委員を共通にするか、それぞれのキャンパスに委員会を設置するかから議論になりました。吉祥寺で夜通し話し合ったのを覚えています。委員が共通だと「2回もやるの?」となるし、2つの委員にすると人数が足りないし。最終的には当時の委員長と学校側が折衝して、1つの委員で両方行うことに落ち着きました。
田村(卒業生)
ちょうど、2年生の終わりの代替りのタイミングでした。
田口(卒業生)
ゼロからのスタートは事前準備もいろいろ大変でした。ブレーカーが上がらないように、有明キャンパス中のコンセントの位置を全部調べて耐えられるアンペアを確認したり、昔は6号館のところは芝生だったのですが、そこに水道工事をして水を引っ張ったり。連絡を取り合うトランシーバーと携帯電話の電波の届くところを調べたり。実行委員の控室が当日使えない問題が発生して、慌てて20メートルの電話線を買ってきて別の部屋に電話を繋いだり。今、話しながらいろいろ思い出してきました。
星野(在学生)
僕らもあったよね。
松島(在学生)
あった。ゲスト控え室が使えなくなった。
星野(在学生)
先輩の頃からの問題、まだ解決していないです(笑)。最初は黎明祭の存在も知らない人が多いわけで、広報も大変だったんじゃないですか?
田村(卒業生)
そう。有明はオフィス街だし、マンションにもポスティングできない。さあ、どうしようと悩んで、国際展示場駅に駅貼りポスターを貼り出したり、アメーバブログとホームページを必死に更新したり。とりあえず知り合いに広めてくださいと、大学のなかでもビラ配りをしたり。当日は、通りかかった人への呼び込みもしたり、子どもから大人までとにかく多くの人に来てもらおうと動いていました。
星野(在学生)
今でも有明での広報は難しいです。僕らはビッグサイトに行く人たちに、こちらもどうですかと呼びかけたり、朝の情報番組の後ろのほうで旗を振って宣伝したりしてました。
田村(卒業生)
そんなことも? その発想はなかった。
星野(在学生)
僕たちのときは摩耶祭も前年がコロナ禍による制限があっての開催だったので、来場者数が伸びてなかったんです。それで、武蔵野キャンパスに近い吉祥寺駅、田無駅、武蔵境駅のサイネージにCMを出すことにしました。僕がゼミ長をしていた発展FSコピーライティングプログラムのメンバーや、他にも映像研究同好会、放送研究部にお願いをして、告知CMをつくって流したんです。結果的に、摩耶祭、黎明祭合わせて7500人ほどに持ち直すことができました。
田口(卒業生)
1回やらないだけで、けっこう忘れられてしまいますよね。僕も社内のイベントを担当しているのでわかります。
星野(在学生)
前年から大学祭を再開して頑張っていたのに、大学の近所の方たちにもそれが知られていなかった。それがショックでした。だからこそ、自分の年では頑張ろうと思ってCMを出したりしました。
「武蔵野大学をもっと世の中に知らせたかった」
ーー実行委員をやってみて、良かったこと、入ったからこそ得られたことはありますか?
松島(在学生)
やっていなかったら、学生生活で自分の学科の人としか関わるタイミングがなかったと思います。大学祭実行委員会に入ったからこそ出会えて、仲良くなれた友だちがいて、今でも一緒に旅行に行ったり飲みに行ったりできる。就職活動の面接でもよく話題に上がったし、自分が思っていた以上に評価していただけました。実は就職活動のことなんて何も考えず楽しむためにやっていた大学祭が、後になって自分に活きていたことを感じます。
星野(在学生)
そうだね。僕は大勢の仲間たちと一生懸命企画してつくりあげてきたものを、当日、お客さんが楽しんでくださっている様子を見たときに、ああ、やって良かったなと思いました。大学の附属幼稚園の園児たちが大勢で来てくれて、楽しそうにはしゃいでいる姿を見たのが特に印象に残っています。
田村(卒業生)
私はいろいろな人の意見を聞けるようになったことが大きいです。いろんな話し合いをするうちに、自分とは違う考え方もあることがわかって、自分の世界が広がった。それは社会人になってからも役立っている気がします。今、舞台照明の仕事をしていますが、音響や演出の方とのチームを組む仕事の仕方にスッと入れているのは、実行委員を経験していたからかなと感じます。
田口(卒業生)
僕は実は、隣の席の人に誘われて始めたんです。もしそこで始めていなかったら僕、4年間面白いこともなく、ただ大学に行って帰るだけみたいな日々だったかもしれない。あの時決断して良かったなあと思います。先生に言われたことをやるのでなく、自分たちでこういうことをやりたいと決めて、それに向かって進んでいく経験は、人生の糧になりました。チャレンジする勇気が身についた気がします。今の仕事でも自分の役割を果たそうと頑張るときや、プロジェクトで指示を出したりする場面で、あのときの経験が役立っているなと思います。
星野(在学生)
今以上に、社会に出てから、この経験が活きているなあと思うようになるのかもしれないですね。今でも集まると、当時の話になるんですか?
田口(卒業生)
当時の話をし始めると、仲悪くなりそう(笑)。
田村(卒業生)
喧嘩が始まる(笑)。でも大体が笑い話になってる。
田口(卒業生)
あの頃の若い気持ちで明日からも頑張ろう!という気持ちにはなるね。
星野(在学生)
僕は実行委員会をやりながらずっと「なぜ大学祭をやるんだろう?」と考えていたんです。別になくても大学生活は送れる。お金をもらえるわけでもない。なぜやると思いますか?
田口(卒業生)
僕らの代でいつも話していたのは、武蔵野大学をもっと世の中に知らしめたいという想いでしたね。これはけっこう本気でした。大学名を言っても「え?知らない」という反応だったけど、今は認知度が高くなって、武蔵野大学と言えば伝わるのを感じます。あの頃の僕らの活動も今につながっていればいいなと。
星野(在学生)
つながっていると思います。千葉県の学生が増えたのは、黎明祭を頑張ってきた実行委員のおかげだと思います。
田村(卒業生)
私は大学祭というお祭りを経験したいという思いで入ったので、自分が楽しめて、かつ他の人にも楽しんで欲しいという思いでやっていました。それがやりがいだし、意義だと思っていました。
星野(在学生)
なるほど。武蔵野大学の学生って、話してみると心の中に熱い魂みたいなものが見えてくる。こういう熱量こそが大学祭の意義なのかもしれないですね。
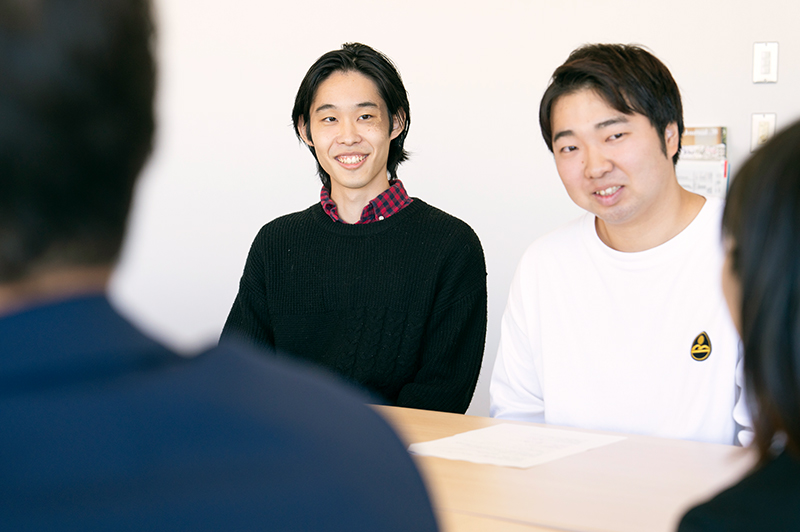
「あの経験、助け合える仲間。今も大切な宝物」
ーー武蔵野大学では、「世界の幸せをカタチにする」をブランドステートメントとして掲げていますが、大学祭をつくりあげるということはどう関係すると思いますか。
田村(卒業生)
13年前の大学祭が今でも友人たちとの会話で出てきます。何年経っても楽しかったという記憶として、大事な経験として私たちの中に残っている。これも、幸せをカタチにすることの一つだったのではと思います。
田口(卒業生)
自分たちでつくっていくんだという思いでやれたこと。そして実際に成功できたこと。そういう学生生活を送れたこと自体が幸せだと思いますし、それを全面的に支援してくれた大学に、ありがたいなという思いがあります。
松島(在学生)
僕がしんどいときは支えようとしてくれる友だちがいて、逆に友だちが困っているときは助けてあげたいと自分が思える。そういう関係性ができたこと。これが大学祭をやることでできた「幸せ」だと僕は思います。大切な宝物です。
ーー今後の後輩たちに伝えたいこと、繋いでいってほしいことは何かありますか。
星野(在学生)
今回の座談会でたくさん違う点が見えてきて、変わっていくのが当たり前だと思った半面、大学祭にかける熱量は同じだと感じました。この想いは自然と伝統として残っていくんだと思います。現役世代は、そういうことを意識せずに、自分たちらしい大学祭に仕上げていってほしい。武蔵野大生には、誇れる才能や個性が一人一人に絶対あるので、それを発揮しながら、失敗を気にせずガンガンやりたいことをやってほしいなって思います。
田口(卒業生)
せっかく限られた機会だからやるからには思い切って発言してみる。そういう気持ちが実際に充実した活動に繋がると思います。
田村(卒業生)
自分たちらしさを出して、引かずに突っこんでいってほしい。やりたいことがあったらやりたいと言ってみる。ダメならしょうがないし、やれることがあるかもしれない。一歩引いてみるんじゃなくて一歩踏み出してみる。勇気を持って踏み出して実行委員会の仕事に取り組んでもらえたらと思います。
松島(在学生)
辞めたいなと思ったときも、一緒に頑張っている仲間とそれを乗り越えたら、絶対何かしら手元に残る。それを信じて活動してほしいです。
摩耶祭・黎明祭の歴史と想い。

今年度で第57回を迎えた武蔵野キャンパスの「摩耶祭」と、第13回を迎えた有明キャンパスの「黎明祭」。特に第1回黎明祭の立ち上げは、様々な規制や苦難を乗り越えるものだったこと、だからこそ実行委員の結束も強く、今でも親密な交流が続いていると田口さん、田村さんは話してくださいました。当時は実行委員会として働く学生のためのお祭りとして、摩耶祭の1日目と2日目の間に「中夜祭」というものがあり、今は難しくなってしまった花火の打ち上げも武蔵野キャンパスで行われていました。この打ち上げ花火は地域の方々にも親しまれ、今でも「もうやらないの?」と地域の方から声をかけられるほど。大学祭を通じた繋がりや想いは実行委員や地域の方々に息づいており、未来にも引き継がれていくことでしょう。
そう思わせてくれる熱量の高いお話でした。

私も大学祭実行委員を務め、星野さんと同じ局に所属していました。ですが、今回の対談を通して、局長だからこそ感じる苦悩や、喜びがあったことを初めて知りました。大変だったと語りながらも、どこか楽しそうに話している様子が印象的で、私ももっと頑張りたかったと思わされるほどの熱量がありました。今回の対談で私自身がいい方向へと影響を受けたように、学生生活に一生懸命取り組んだことが誰かに届く。武蔵野大学の「響き合って、未来へ」に繋がるものがあると感じました。
僕は大学祭実行委員に入っていたわけじゃないので、お話を聞いて初めて知ることが多く、楽しかったです。特に、第1回目の黎明祭は、ブレーカーの落ちないコンセントや電波の届く場所を探すところから始めたというのが、本当に驚きでした。卒業生の方も、在学生の方も、和やかに、でも熱い魂を交えて当時を振り返っていて、何かに打ち込んで得られるのはこの熱さなのかもしれないなと感じました。そして、今回の記事が、読んでくださった方の何か熱い取り組みのきっかけになったら幸いです。
大学祭実行委員を務めた代は違っても、同じ責任感を持って大きなイベントを成功させた。そんな皆さんのお話を聞いて、学生時代において何かに打ち込み仲間と協力することがいかに貴重な経験かを改めて知る機会になりました。大学祭実行委員をやることで生まれた交流が、今でも皆さんの中で大切なものになっているとお話されていたのが印象に残っています。私も今後の大学生活で、夢中になって取り組むことのできる“何か”に出会いたいと感じる貴重なお話を聞くことができ、嬉しく思います。
過去の大学祭の情景と、慌ただしい準備の様子が脳裏に浮かんでくる、そんな座談会でした。それぞれの方の役割に対する思いや、「絶対に成功させるぞ」という4人の熱量が、お話が進むにつれてどんどん大きくなってきて、聞いている立場でもどこか緊張感さえ感じました。原稿制作にあたっては、大学祭という大きなプロジェクトのリーダーを務め、全体を統括した4人の、余裕のある心持ちや熱量を感じてもらえるように心がけました。
取材日:2024 年11月 所属・肩書等は取材当時のものになります。

